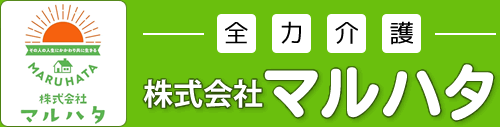← 代表挨拶 に戻る
新しい選択肢
認知症患者の現状
現在の認知症患者は独居生活を送ることが困難、在宅での家族の関わりが困難な為、周囲とトラブルに至る可能性が高く、それを回避するため、病院・施設に入る・入っている方がほとんどである。家族としては家族の代わりにスタッフに見てもらえる、急変しても対応してもらえるという安心感や、自分たちの生活を過ごせるといった安堵感を少なからず感じることができる。しかし、当の本人たちは病院・施設の決められた日程に沿って、決められた時間で、決められたことを行っている現状を必ずしも好んでいなかったり、「ここしか行く場所がない」と自分に言い聞かせ諦めている現状がある。
自分の人生を好きなように生きたい、自分の家・部屋で暮らしたい、自分で死に場所を決めたいという思いがあり、病院・施設に対して「ここは嫌だ」「家に帰りたい」と思っている方がほとんどである。すべて管理されている方が楽と考える方もいるが、好きな時に起き、好きな時に食事を摂り、好きな時に入浴し、好きな時に寝る、という生活していく上での当たり前の欲求を、病院・施設のルールに沿って行動しないと急かされる、介助という名で強引に行われるために、やりたいときにやれない・やりたくないのにやらされるという不満を抱えている方が多い。
認知症患者はそういった気持ちの表現方法が乏しいため、嫌だという気持ちをうまく伝えられずに「手を出す」という表現方法をとる事が多い。そういう方たちを医療従事者は単純に「暴力行為」「調子が悪い」ととらえ不調・不穏時の頓服を使用し鎮静を図ったり、逆に周辺症状が見られない時は「穏やか」「落ち着いている」と判断し特変のある患者にばかり関わりスルーしている現状がある。さらに「安全・安楽に」という考えから医療従事者が考える危険行為に当てはまる事・当てはまりそうな事は事前に対処しようと働きかけ、「自分でやる」という気持ちや行動を削いでしまっている状態がある。その現実が認知症患者の「出来ること」を奪っているため、患者さんのADLを落とす原因であり、認知機能の低下を招き最終的に寝たきりにさせてしまう事に繋げてしまっている。
認知症を患っている方とその家族の現状
(社会から向けられている認知症患者への視線の変化に対する弊社の考え)
家庭という共同体がありその中で子供たちが成長し、新たにそれぞれの家庭(共同体)を築き上げていくというごく自然な社会の流れがある。しかし、その中で残された親が認知症を患うことで社会性を失っていくという現実がある。新たな共同体を築いた者はその共同体を守るという責任があり、それと同時に現在の自分を築き上げたかつての共同体(親・家庭)に対する愛情と感謝を世間体や自身の自尊心と重ね、「自分の親に限って」「まさか認知症になる訳がない」という考えや「人様の前に出すのが恥ずかしい」「隠したい」という考えに至る傾向がある。そのため、認知症そのものを否定し、認知症による周辺症状に対しての理解が困難となるケースが多くみられます。本意ではない言葉や態度で親を責め、親は責められた事にさらに症状を悪化させ、互いにうつ病を併発することも多くみられます。症状の進行により悪化しエスカレートしていく言動・行動が両者を悩ませ、この状態が日々繰り返されていき、身体的にも精神的にも疲弊していくという現状があります。
認知症の周辺症状により日常生活が困難になると社会からは可哀そうという憐れみの視線が向けられ支援の対象となるが、認知症が進行することで迷惑行為といわれる暴言・暴力・徘徊等により社会から向けられる視線は危険・トラブルメーカーといように変化し淘汰・排除する対象となります。
誰もがかつての共同体(親・故郷)への感謝の念を抱いていながらも、日々の生活に追われその想いを表現する機会をなかなか得られずに生活しています。
ほとんどの親は子に助けを求めることにとても抵抗を感じると思います、そこに認知症という疾患が重なり、自分の身に起きていることを素直に受け入れられず打ち明けらなれない相談できないという現状があります。この現状を、認知症という疾患を不治の病だ、悲しい現実だ、と捉え目を背け諦めるのではなく、親孝行をするチャンスを与えてもらったと考えることで、認知症に正面から向き合いこれからの介護のありかた、認知症の方に対する家族・社会の関わり方を変えたいと考えております。
シェアハウスとは
弊社の考えるシェハウスの必要性について
- 結論
- 様々な理由で既存の施設や制度を等しく享受できていない方が居る現状に対し、その方たちも含めたすべての人々に分け隔てなく人間として尊厳を保った生活を送ることのできる場(シェアハウス)が必要
- 現状
- 認知症患者や障がいをもつ方は独居生活が困難であり、多くの方々が保険制度を利用し施設での生活やデイサービス等を利用している。
大きく分けて下記の状況と考える
- 家族の支援と訪問介護等のサービスを利用し独居生活を継続
- グループホームやサ高住へ入居する
- 特養へ入所する
- 老健へ入所する
- 病院へ入院する
- 身寄りがなく相談する相手や支援の受け方を知らず困難でありながらも独居生活を継続する
- 問題点
- 1~5の既存の施設やサービス制度があるなかでの問題点は下記の通りと考える
- 家族の介護負担増
- グループホームやサ高住→入居費用とその他にかかる費用が高い(おむつ代や病院受診代等)
- 特養→需要に対し供給が足りない(入居の待機が多い)
- 老健→入所期間に定めがある
- 病院→退院がある(そもそも治療の場であり生活の場ではない)
以上と6の状況を踏まえて弊社が考える問題としては下記の通り
- 本人や家族が介護保険制度の利用方法について詳しく知らない、介護保険制度の利用に抵抗がある
- 経済的理由により既存の施設や制度を利用できない(介護保険を利用しても支払えない人も多い)
- 24時間、365日の介護で家族が疲弊し、日々の生活や精神状態に影響を及ぼし互いの関係性に歪みが生じ、それにより事件や事故に至る可能性が高まる
- 対策
- 弊社で考える対策としては下記の通り
- 介護保険制度に詳しいスタッフが相談・対応できる
- シェアハウスの入居費用設定を、月/10万円~ +1割負担金とし、その他病院受診・送迎なども相談に応じ、経済的に余裕のない方でも利用できる設定で行っている
- 24時間、365日対応できるシフトを組んでいるため、スタッフが利用者や家族からの深夜・早朝の要件も対応できる
← 代表挨拶 に戻る